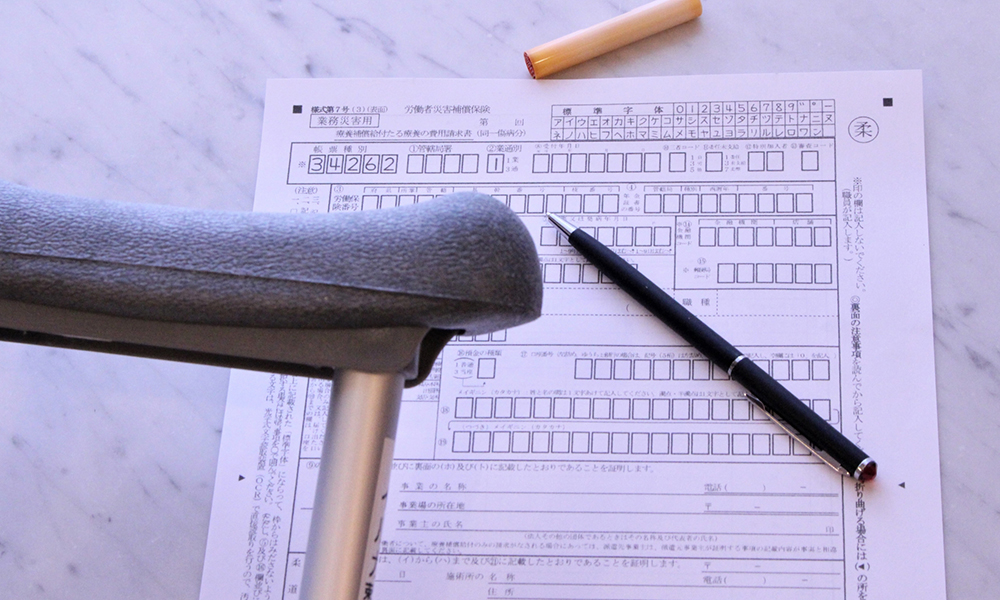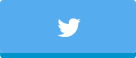いくら安全に気をつけていても、病気やけがに見舞われるときがあるものです。
労働者の万一の傷病のために、労災保険という制度があります。そして、労災保険では必要に応じて、さまざまな保険給付が行われています。
この記事では、労災保険、および療養(補償)給付、休業(補償)給付について解説します。
労災保険とはどのような保険制度か
労災保険制度とは、労働者の業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害などに対して必要な保険給付を行うものです。
労働者災害補償保険法に基づいており、労働者の社会復帰の促進、その労働者と遺族の援護、労働者の安全および衛生の確保などを図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
原則として、労働者を1人でも使用している事業であれば、労災保険が適用されます。>
この「労働者」には、正社員だけではなくアルバイトやパートタイマー、派遣労働者も含まれます。労災保険は、企業の業種や規模、あるいは労働者の雇用形態にかかわらず、適用されるのです。
なお、労災保険料は、事業主が全額を負担することになっています。
傷病などの事由が業務上のときは「業務災害」、通勤によるときは「通勤災害」と呼ばれます。
また、複数の会社で働くなど、ダブルワークをしている労働者もいるでしょう。>
事業主が同一ではない複数の事業場で同時に使用されている労働者を、「複数事業労働者」と言います。
労働者が業務または通勤が原因で、負傷したり病気にかかったりしたときは、労災保険から保険給付が行われます。
労災の保険給付は、基本的に、労働者本人が労働基準監督署に請求します。その請求を認め、保険給付を行うかどうかは労働基準監督署長が決定します。
もしも、保険給付を請求するうえで必要な事業主証明を会社が拒否したとしても、請求自体は可能です。
労災保険には、下記のような保険給付が設けられています。
- ●療養(補償)給付
- ●休業(補償)給付
- ●傷病(補償)年金
- ●障害(補償)年金・障害(補償)一時金
- ●遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金)
- ●葬祭料・葬祭給付
- ●介護(補償)給付
- ●二次健康診断等給付
- ●特別遺族年金・特別遺族一時金
ちなみに、労災保険では保険給付のほかに「社会復帰促進等事業」も行われています。
この記事では、はじめにお伝えしたとおり、「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」についてご説明いたします。
療養(補償)給付とはどのような保険給付か
療養(補償)給付とは、業務上または通勤による傷病で、療養が必要なときに支給される保険給付です。
業務災害であれば「療養補償給付」が、通勤災害であれば「療養給付」が支給されます。複数事業労働者の、複数の事業の業務を要因とする業務災害であれば「複数事業労働者療養給付」が支給されます。
業務災害として認められるためには、業務と傷病の間に一定の因果関係がなくてはいけません。たとえば、下記のような点が判断のポイントとなります。
●事業主の支配・管理下で業務に従事していたか
●労働の場に有害因子(有害な物理的因子・化学物質・病原体など)が存在していたか
複数事業労働者療養給付の場合は、複数の事業場での業務上の負荷(労働時間やストレスなど)を総合的に評価し、判断することになっています。
一方、通勤災害として認められるためには、就業に関して、下記のような移動を合理的な経路および方法で行っていなくてはいけません。
●住居と就業場所との間の往復
●就業場所から他の就業場所への移動
●住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動
療養(補償)給付の給付内容には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。
「療養の給付」とは、労災病院や労災指定医療機関・薬局などで療養を受けるときに、無料で治療や薬剤の支給を受けられること(現物給付)です。
「療養の費用の支給」とは、労災病院や労災指定医療機関・薬局など以外で療養を受けたときに、その療養の費用の支給を受けられること(現金給付)です。
どちらの支給を受けるにしても、対象となる範囲や期間は変わりません。療養(補償)給付の支給期間は、傷病が治癒するまでです。
労災保険で言う「治癒」とは、かならずしも傷病が回復したことを指すわけではありません。傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(症状固定)を言います。
さらに、通院費が支給されることもあります。ただし、同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がなく、居住地または勤務地から片道2キロメートルを超える通院しているなど、一定の要件を満たしている場合に限られます。
療養の費用の支給には、請求の時効が定められています。費用の支出が確定した日の翌日から2年を経過すると、請求権は消滅してしまいます。
療養の給付は現物給付なので、請求権の時効を気にする必要はありません。
休業(補償)給付とは、業務上または通勤による傷病で休業しているときに支給される保険給付です。
業務災害であれば「休業補償給付」が、通勤災害であれば「休業給付」が支給されます。複数事業労働者の、複数の事業の業務を要因とする業務災害であれば「複数事業労働者休業給付」が支給されます。
休業(補償)給付の支給を受けるためには、以下の要件を満たしていなくてはいけません。
●業務災害または通勤災害による傷病のために療養している
●労働することができない
●賃金を受け取っていない
休業(補償)給付は、休業の4日目から支給が始まります。休業の1日目から3日目までは、待期期間となっています。そのため、休業(補償)給付は支給されません。
ですが、業務災害の場合、事業主にはこの間の休業補償を行う義務があります。通勤災害および複数の事業の業務を要因とする業務災害に関しては、この補償は義務づけられていませんので、ご注意ください。
休業(補償)給付の支給額は休業1日につき、給付基礎日額の60パーセント相当額と決まっています。
「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法で定められている平均賃金に相当する額です。「平均賃金」とは、簡単に言えば、直前の3カ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、歴日数で割ったものです。
休業(補償)給付には、「休業特別支給金」が上乗せで支給されます。休業特別支給金の支給額は休業1日につき、給付基礎日額の20パーセント相当額です。
複数事業労働者休業給付の場合は、複数の事業場での給付基礎日額に相当する賃金を合算して、算出に用います。
複数事業労働者休業給付は、給付基礎日額を合算した額の60パーセント相当が支給されます。同じように、休業特別支給金も給付基礎日額を合算した額の20パーセント相当が上乗せで支給されます。
一点注意していただきたいのが、休業給付に関しては「一部負担金」があることです。
通勤災害で療養給付の支給を受けている労働者は、初回の休業給付から200円減額されます。
休業(補償)給付にも、請求の時効が定められています。休業(補償)給付は、支給対象となる日ごとに請求権が生じます。請求権が生じた日の翌日から2年を経過すると、請求権は消滅します。
昨今、コロナウイルスの影響からテレワークを導入する会社も増えています。
テレワークで在宅勤務などをしている労働者であっても、要件さえ満たせば、労災の保険給付を受けることは可能です。
労災について気になる方は、厚生労働省のホームページや労働基準監督署などで、さらにくわしい情報をご確認ください。