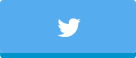2021年度の税制改正で、退職所得課税の適正化が決定されました。勤続年数5年以下の従業員に対する退職所得税制が見直されたもので、2022年分の所得税から適用される予定です。
この記事では、退職所得にかかる税金と節税の仕方、また税制改正の概要について解説します。
退職所得にかかる税金は?
退職所得には所得税及び復興特別所得税、住民税がかかります。
- ●所得税及び復興特別所得税
(退職金の額-退職所得控除)× 1/2=(課税退職所得金額)
(課税退職所得金額)×(所得税の税率)-(控除額)=(所得税額)
(所得税額)+(基準所得税額)× 1%=(所得税及び復興特別所得税額) - ●住民税
(課税退職所得金額)× 10%=(住民税額)
一般的に、退職金の受け取り方は「一時金」とする方法と、「年金」として受け取る方法があります。受け取り方によって課税関係が変わってきますので、まずは勤務先の退職金制度を確認することが大切です。退職金規定で、「一時金のみ」と定められていれば選択の余地はありませんが、ご自身で決められるケースも多くあります。
退職金を一時金としてまとめて受け取る場合、先に記述した退職所得として扱われます。退職所得は長年の勤労への対価であるとして、勤続年数が長いほど税負担が軽くなるように配慮されています。
また、分離課税として計算されるため、退職後に国民健康保険に加入する際の保険料の算出基準となる所得に含まれません。
退職金を年金として分割して受け取る場合は、「雑所得」として取り扱われることになります。
「雑所得」は、公的年金等、生命保険契約等に基づいて支払われる年金、副業にかかる所得などが該当します。受け取る年金が「公的年金等」に該当するケースでは、公的年金等控除額を収入金額から差し引いたものが公的年金等の雑所得となります。
雑所得は総合課税の対象であるため、給与所得や不動産所得など他の所得があるときは、それらと合わせて課税されます。
一括でもらう場合と分割してもらう場合、どちらが良いのかということに関しては、ケースバイケースですが、節税という観点から考えれば、多くの場合一時金として受け取るほうが良いと考えられます。
理由としては、前述したように退職所得が税制上大きな優遇をうけていること、受け取った年で税金の清算が完了することによります。
勤続年数38年60歳で定年を迎えるAさんを想定し、同じ年の配偶者がいると仮定します。また、収入や退職金、年金などは以下のように設定します。
- ●再雇用により64歳まで年間200万円の給与収入
- ●退職金は2,000万円。年金として受け取る場合は60歳から20年間、年116万円ずつ受給
- ●厚生労働省からの年金は65歳から79歳まで年間200万円の受給
なお、配偶者には収入はなく、控除は社会保険料控除、配偶者控除及び基礎控除と仮定します。 社会保険料は収入の15%もしくは東京都杉並区を参考に算出した概算値です。
以上のようなケースで、退職金を一括で受け取った場合と分割してもらった場合の税額等を試算してみます。今回、復興特別所得税は考慮しないこととします
79歳までの収入は退職金+再雇用時の給与収入+厚生労働省からの年金収入と計算されます。
したがって、2,000円+1,000万円+3,000万円=6,000万円 となります。
勤続38年なので、2,060万円までは非課税となります。よって、退職金2,000万円には税金がかかりません。60歳以降20年間の1年あたりの税金額等は、以下の通り算出されます。
| 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間収入 | 給与 | 200万円 | |||
| 年金 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | ||
| 年間所得 | 給与 | 132万円 | |||
| 年金 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | ||
| 控除 | 配偶者 | 38万円 | 38万円 | 48万円 | 48万円 |
| 社保 | 30万円 | 20万円 | 15万円 | 10万円 | |
| 基礎 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | |
| 合計 | 116万円 | 106万円 | 111万円 | 106万円 | |
| 課税所得 | 16万円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 所得税 | 0.8万円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 住民税 | 2.6万円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
79歳までの収入は、再雇用時の給与収入+厚生労働省からの年金収入+企業年金収入で計算されます。したがって、
1,000万円+3,000万円+2,320万円=6,320万円 となります。
| 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間収入 | 給与 | 200万円 | |||
| 年金 | 116万円 | 316万円 | 316万円 | 316万円 | |
| 年間所得 | 給与 | 132万円 | |||
| 年金 | 56万円 | 206万円 | 206万円 | 206万円 | |
| 控除 | 配偶者 | 38万円 | 38万円 | 48万円 | 48万円 |
| 社保 | 30万円 | 36万円 | 36万円 | 25万円 | |
| 基礎 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | |
| 合計 | 116万円 | 122万円 | 132万円 | 121万円 | |
| 課税所得 | 72万円 | 84万円 | 74万円 | 85万円 | |
| 所得税 | 3.6万円 | 4.2万円 | 3.7万円 | 4.25万円 | |
| 住民税 | 8.2万円 | 9.4万円 | 8.4万円 | 9.5万円 | |
一括で受け取った場合と違い、60歳以降ずっと所得税や住民税が課されることが推測できます。
一時金として受け取った場合と年金として受け取った場合を比較してみると、79歳までの収入では320万円年金として受け取る方が多くなりますが、税金面を見てみると、退職金を一時金として受け取るほうが節税できていることが明らかです。差し引きすると、一時金として受け取った場合の方が、100万円以上手取り額が多くなります。退職金を受け取る際は、受け取り方によって、手取り額にかなり差ができてしまうということを念頭に、今後のことを考えて選択することが大切です。 上記はあくまで試算のため、詳しく相談したい場合は顧問税理士や管轄の税務署に尋ねてください。
退職所得を算出する際、退職所得控除後の金額に2分の1をかけることについて、勤続5年以下の従業員についても制限が加えられることとなったことが変更点です。 具体的には、勤務年数が5年以下の従業員に支払われる退職金(短期退職手当等)から退職所得控除額を引いた残りの金額のうち、300万円を超える部分について2分の1を乗じないこととなったのです。退職所得の計算式は次のとおりです。
- 収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 - 収入金額-退職所得控除額>300万円の場合
150万円+(収入金額-退職所得控除額-300万円)=退職所得の金額
退職所得控除額は、40万円×5年=200万円、また、退職所得の金額は以下のように計算されます。
なお、この改正は2022年以降の所得税について適用されます。会社役員等に比べ少し優遇されてはいますが、控除後の金額に2分の1をかけるという条件がないことは相当な負担となると考えられます。転職や独立の時期を検討する必要が出てくるでしょう。
退職金の受け取り方には2通りあり、その受け取り方で課税関係や将来的な手取り金額が変わるので、自身の状況等鑑み、よく検討することが大切です。